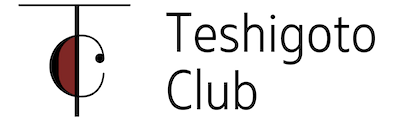伝統工芸について


木曽漆器(きそしっき)
木曽漆器 江戸時代の中期に、中山道を往来する旅人を相手に、豊富に産出するヒノキ、桂、栃などを材料として、曲物、ろくろ細工、櫛といった日常雑器を作り始めたのが始まりで、これらが旅人により京都、大阪、江戸へ運ばれ、認知度を高めてきたといわれる。
木曽漆器(きそしっき)
木曽漆器 江戸時代の中期に、中山道を往来する旅人を相手に、豊富に産出するヒノキ、桂、栃などを材料として、曲物、ろくろ細工、櫛といった日常雑器を作り始めたのが始まりで、これらが旅人により京都、大阪、江戸へ運ばれ、認知度を高めてきたといわれる。